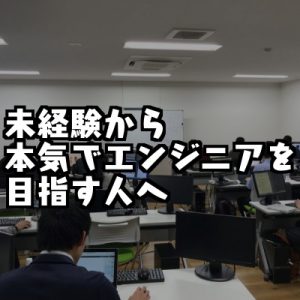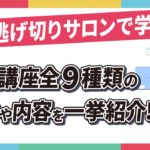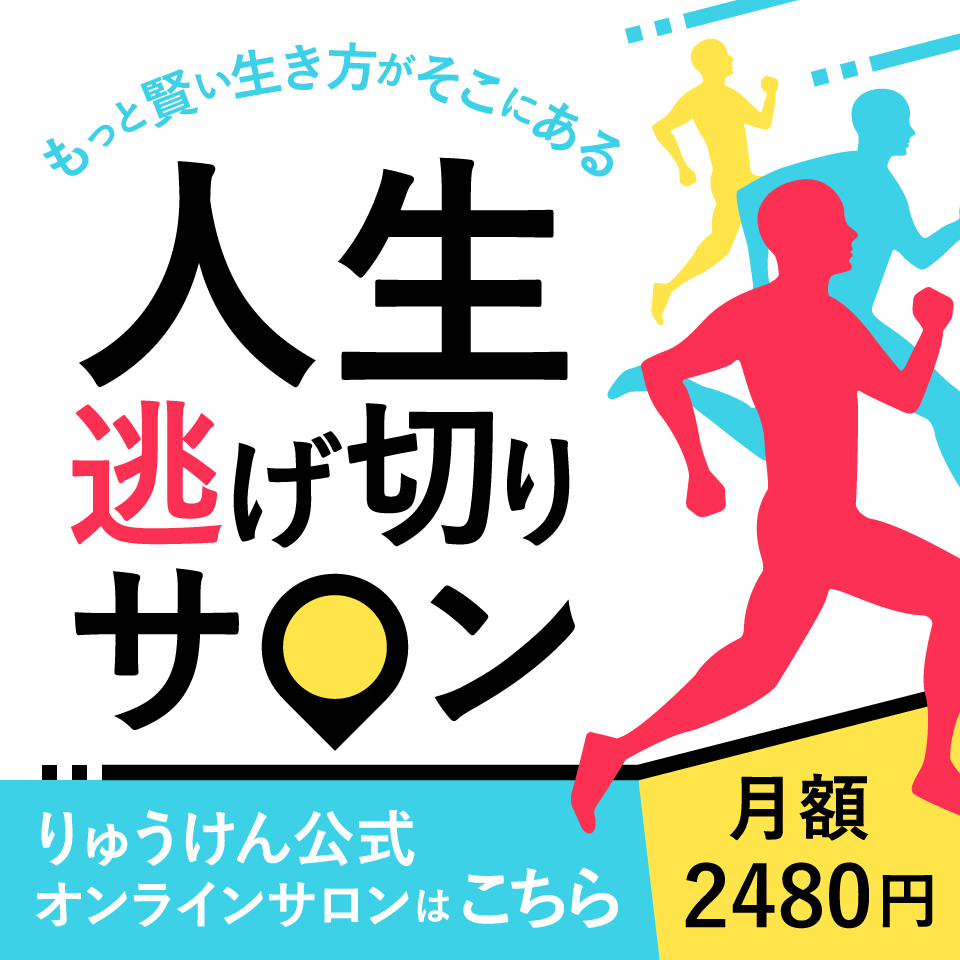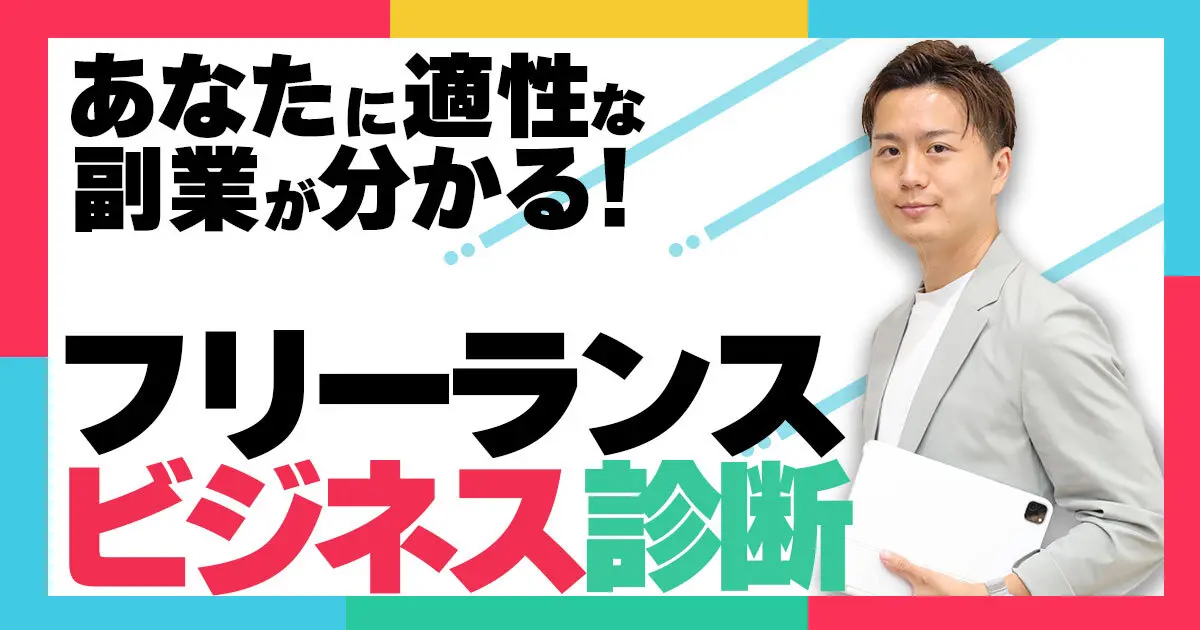どうも、160名以上が参加するオンラインサロンのオーナー、りゅうけんです。参加者1万人目指してます。
ところで、オンラインサロンのような「私塾的有料コミュニティ」の運営って結構高度な技術が要求されるの知ってました?大学生のサークルとも、会社組織とも違う、この特異なコミュニティの運営は一筋縄ではいきません。
色んなサロンに入ってみたり、自分でもやってみるとわかるんだけど、パリピがノリと勢いだけで運営しても当然行き詰まるし、かといって、経営者や優秀なサラリーマンがその類稀なるマネジメントスキルを発揮したからうまくいくというわけでもないんですよ。オンラインサロンとは非常にシビアなビジネスです。
SynapsとかDMMみたいなプラットフォーマーのおかげでオンラインサロンがカジュアルに始められるようになったのはとても素晴らしいことだけど、舐めてかかると苦労するよね。そりゃこれだけゾンビサロンも多いわけだ。
今回はオンラインサロンを実際に運営してわかった、私塾的有料コミュニティ運営の基本的考え方についてお話ししていこうと思います。
目次
1.参加者を管理しない
オンラインサロンを繁盛させるためには参加者を「管理」してはいけません。これ、仕事できる人ほどやっちゃうんですよね。普段のノリで。
まず前提として、管理されたい人ってこの世に存在しないんですよ。
「俺、頑張るんで厳しいこと言ってください!」みたいな言葉を信用して、本当に上司みたいになって管理しちゃダメです。彼らの言葉はただの「音」です。少なくとも本人の行動が伴わないうちは信じるに値しません。
彼らのその決意は、あなたに好かれようとするための「見栄」だから。もちろん本当にコミットしてるわけではないし、実際に厳しいこと言うと逃げ出します。ここらへんの「距離感」が掴めてない人が多いんですよ。相手の気持ちになれてないということ。
そして、管理の中でも特にやっちゃいけないのが、「他人との比較」。これはやばい。
「あいつはもっとやってたで」とか「俺はもっとやってたで」とか言っちゃうとプライド傷つけます。「プライドなんてズタボロにしてなんぼや!」とか思ってる人もいるだろうけど、お金払ってまでわざわざしんどい思いなんてしたくないのが人間やでっていう。
これが会社組織であれば「管理」は有効な手段なんですよ。会社組織は「固定給の配布」という形で参加者に対する生殺与奪の権利を持っているため、アホみたいに詰めても誰もやめません。むしろ、辞める前に死ぬ人だっています。
しかし、オンラインサロンのような自由に出入り可能なコミュニティには基本的には人を環境に縛り付ける力はありません。オーナー側は飽くまで「参加者側に決定権がある」ことを忘れてはいけないんですよ。
2.管理するのではなくリードする
管理せずにではどうやって参加者のモチベーションをコントロールするのか。答えは「リード」することです。
オーナーが「これをやってください」と言えば、参加者に特定の作業をやらせることは可能でしょう。しかし、それは参加者にとって、「外から火をつけられている状態」にすぎません。本人が心からその作業をやりたいと思ってやっているわけではないということ。
口で言ってやらせても、「言わないとやらない人」が出来上がるだけでコミュニティの自律的成長には貢献しません。これでは意味がない。
僕らは指示することをやめ、自分の姿勢で感化させるんです。自分自身が他の誰よりも新しいことに挑戦し、変化していくこと。それを見てはじめて、参加者は「内側から火がついた状態」になっていきます。
ある意味単純な話です。参加者を稼がせたかったら、あなた自身が今以上に稼げばいいし、参加者をモテさせたかったら、あなた自身が今以上にモテればいいだけです。自分自身の姿勢が良くも悪くもまるっとコピーされて勢い良く伝播されていく世界。
ところが、環境を提供するだけで、参加者の成長に一切責任を負わないオーナーってたくさんいるんですよね。コミュニティは「誰かに盛り上げてもらう」のではなく、「自分が盛り上げる」んです。今時、ねずみ講の親玉でもこんなことわかってるんだけど。
率先して自分が動き、場が盛り上がり始めたなら、次は積極的に参加者を評価しましょう。頑張っている人がいたら、彼らをスレッドなどでピックアップしてあげるといいですね。自分では感化させられない人も、彼らなら感化させられるかもしれません。
他人の力を借りてコミュニティを発展させていく感覚が掴めてきてようやく、ほんの少し手が離れ出すんじゃないかと思います。
3.コミットを強要しない
宇宙にはパレートの法則とかいう厄介な法則があります。どんなコミュニティでも熱心に頑張るのはそのうちの2割で、後の8割はぼーっとしてるよっていうアレ。
これはもう、そういうもんとして割り切るしかありません。8割側のぼーっとしてた人達が急に目覚めて頑張りだしたかと思うと、それまで2割側で頑張ってた人のテンションがいつの間にか落ちて、結局2:8の割合が維持されてる不思議。なんなんやろ。誰か量子力学とかで解明してくれ。
意識高い人なんかは全員やる気MAXメンバーで固めようとしがちなんだけど、結局この法則には逆らえず2割と8割に分かれてしまいます。すると、「やる気のある奴だけついて来い」って言っちゃったもんだから、8割側におちた人の居心地が悪くなって、コミュニティから人が抜けていきます。
大事なのはこのパレートの法則とうまく付き合っていくことです。気合い入ってる2割を徹底的にフォローしつつ、8割の非アクティブに「そこにいるだけでも」価値を感じてもらえるようなコミュニティづくりを目指します。
2割側の能動的アウトプッターが環境に価値を感じるのはある意味当たり前です。8割側のレシーバーにすら満足させ、低解約率を維持できてこそプロ。かくいう僕も完璧にできているとは言い難いんですが。
例えば、貸し会議室が無料で使えるようにしたり、転職時に有利になるように口利きしてあげるみたいな物理的便益でサロン会費以上のリターンを提供するなどはわかりやすいでしょう。
究極的には、オンラインサロンへ参加していること自体に価値を感じさせられたら無敵でしょうね。オンラインサロンのブランド化。これができれば積ん読(参加したけど完全放置している人)ですら満足させられるでしょう。ただしこれは超難易度高いです。
4.人を知る
コミュニティ内の動きを把握することは重要です。参加者の年齢、仕事、趣味、動機、大まかな居住区、どのスレッドでどの時間帯によく発信しているか、くらいは最低限把握しておきたいですね。もちろん本人が公開してくれてる範囲でですけど。
なぜこれらの情報を収集するかというと、ここにコミュニティの質を高めるヒントが詰まっているからです。
情報を掌握すれば、サロン内の誰と誰をマッチングさせたら相乗効果が生まれるかがわかるんですよ。共通点の多いもの同士をうまく繋げると、本人達にとって居心地の良い環境をつくることができます。特に女性ユーザーにはその傾向が強いですね。
ただ、モチベーションの低い人同士をくっつけると馴れ合いになってしまうので注意は必要です。新しい参加者にとって、最も刺激になる人物を即ピックアップできるよう、常にマッチングを見据えてサロン全体を見渡しておくこと。
また、オーナー自身が単純に参加者を知れば知るほど具体的なアドバイスがしやすくなるので、顧客満足度が上げやすいです。
実はコミュニティ運営で一番労力をかけるべきなのはここなんです。「人を知る」こと。慣れないうちは30人くらいでもあたふたすると思いますが、自分のキャパはサロン参加人数の増加に比例して面白いほど広がっていくので心配ありません。
人によるとは思いますが、個人的には500人くらいまでならくまなく把握できるんじゃないですかね。
5.言いたいことは誰かに言ってもらう
誰かに何かを言いたい時は、できるだけ直接自分で言わないようにしてください。自分で言うことほど説得力のないことはないから。なので、誰かにあなたの代わりに言ってもらうんです。つまり、「引用する」ということ。
「成功するためには周りの目を気にしてたらあかんで。」と言うくらいなら、「ジョブズがステイフーリッシュって言ってたで。」と言う方が聞き手は納得できるんです。あなたの言葉ならともかく、ジョブズの言葉ならとりあえず聞いとこかってなるわけ。
これはあなたに人望がないとかそういう話ではなく、目の前の人が言うことを素直に聞けないのが人間なんですよ。距離が近くなると悪い意味で慣れてしまうから。リスペクトは時間とともに確実に薄れていきます。
だって、僕らはジョブズの名言を有難がって聞いてるけど、実際にジョブズの下で働いてた人は有難がるどころかジョブズをアップルから追放しちゃったわけでしょ。自分の影響力を過信して強い主張を繰り返すと禍根が生まれるんです。
だからこそ、言いたいことは自分で言ってはいけません。誰かに代弁してもらいましょう。
コミュニティ内で何かを主張する際は、積極的に外部メディアの情報を引用していくこと。キュレーション力が試されますね。
さいごに:オンラインサロンの開設を激しくおすすめする
最終的にはみなさんにもオンラインサロン、もしくはオンラインサロンのような私塾的有料コミュニティの運営に挑戦してもらうことをおすすめしています。
というのも、やっぱり主催者が一番多くの情報を受け取れるんですよ。自分でいうのもあれだけど、サロンはじめてから知見が急拡大しました。初期の頃とは別人です。
うちのサロンでは、ブロガーだけでなく、ネット物販や資産運用のベテラン達など、各界の猛者達が惜しげもなくその知見を披露してくれます。そんな環境において、オーナーである僕が成長しないわけないじゃないですか。今なら何やっても稼げると思いますよ。
サロン運営は定期収入が得られるということ以上に、「自分がなりたい自分に、みんなの力を借りてなれる」というのが魅力だと思っています。
上記の通り、サロン運営は決して簡単なものではありませんが、想像以上のリターンが得られるのは間違いないのでぜひ挑戦してみてください。