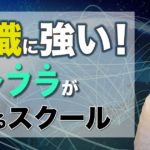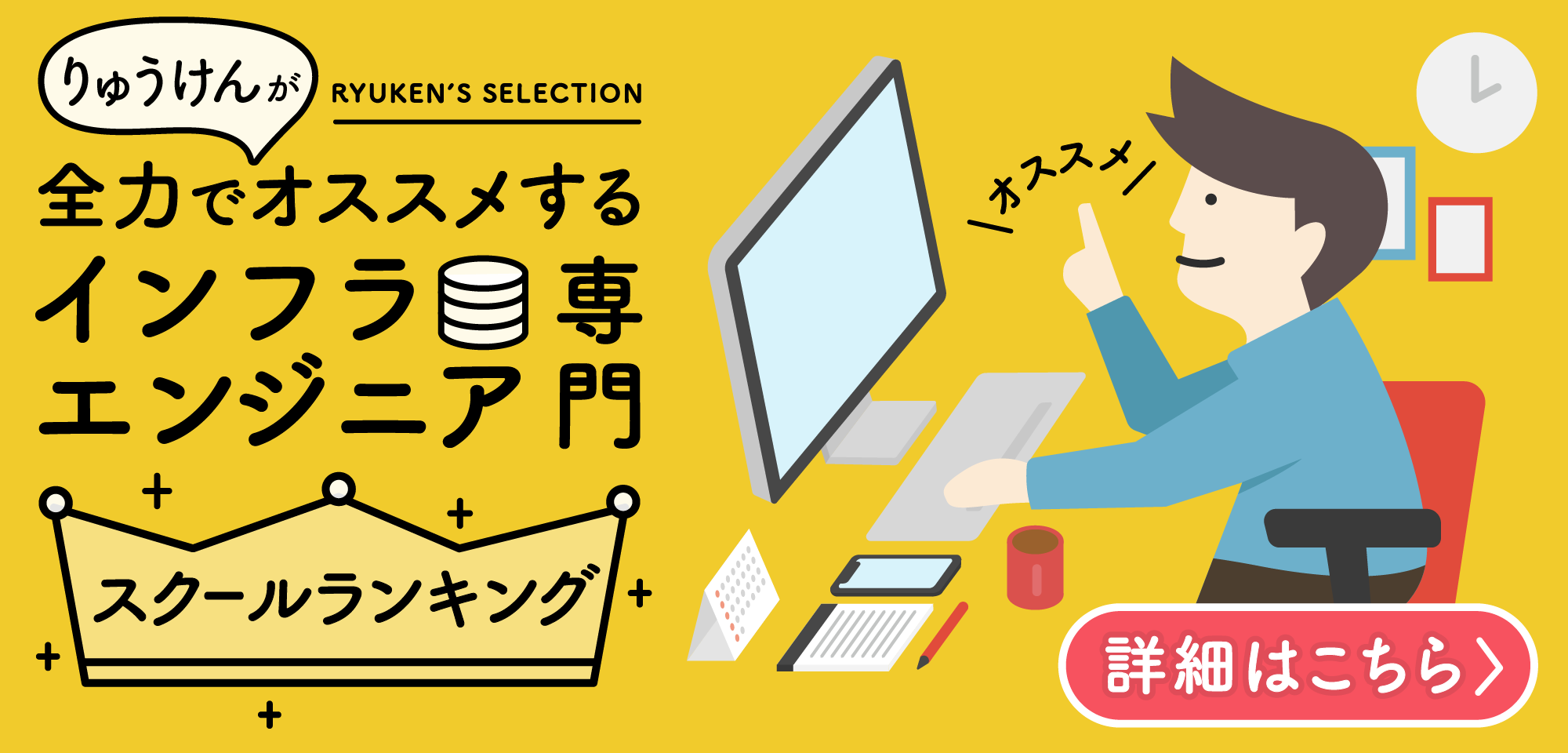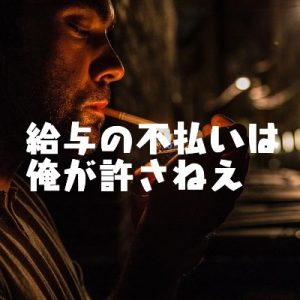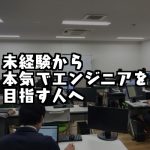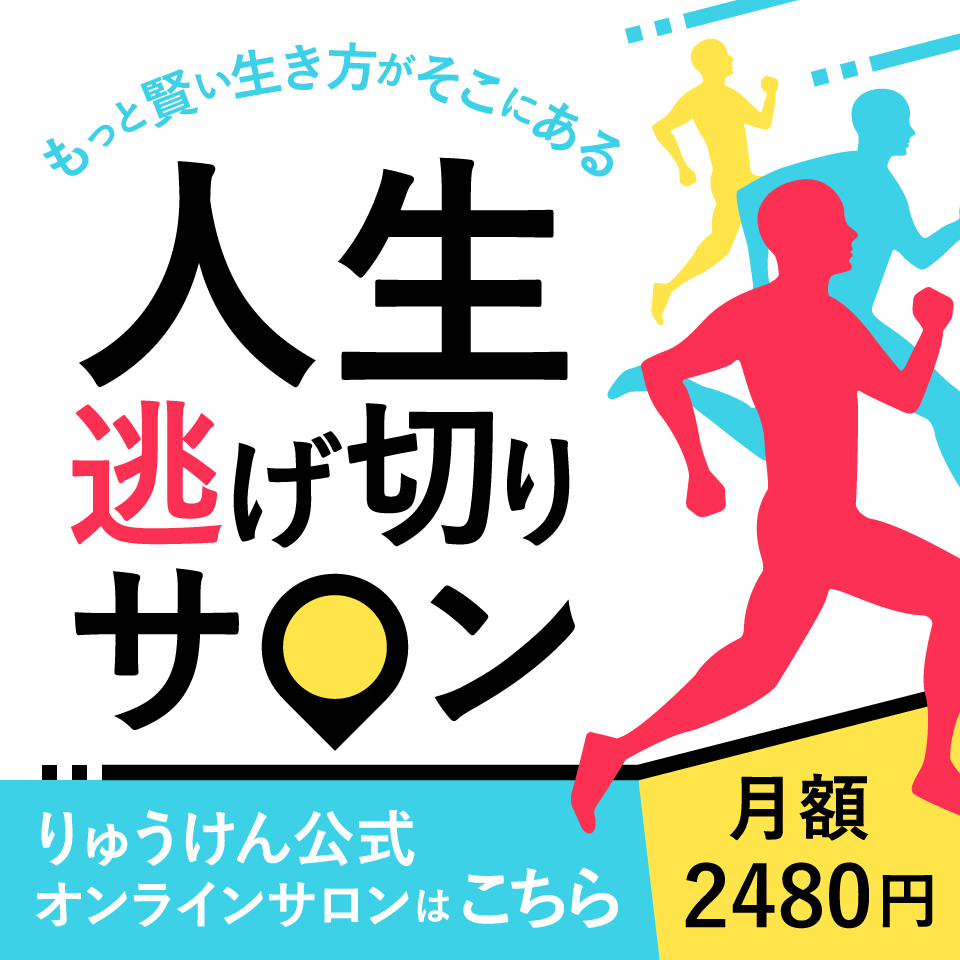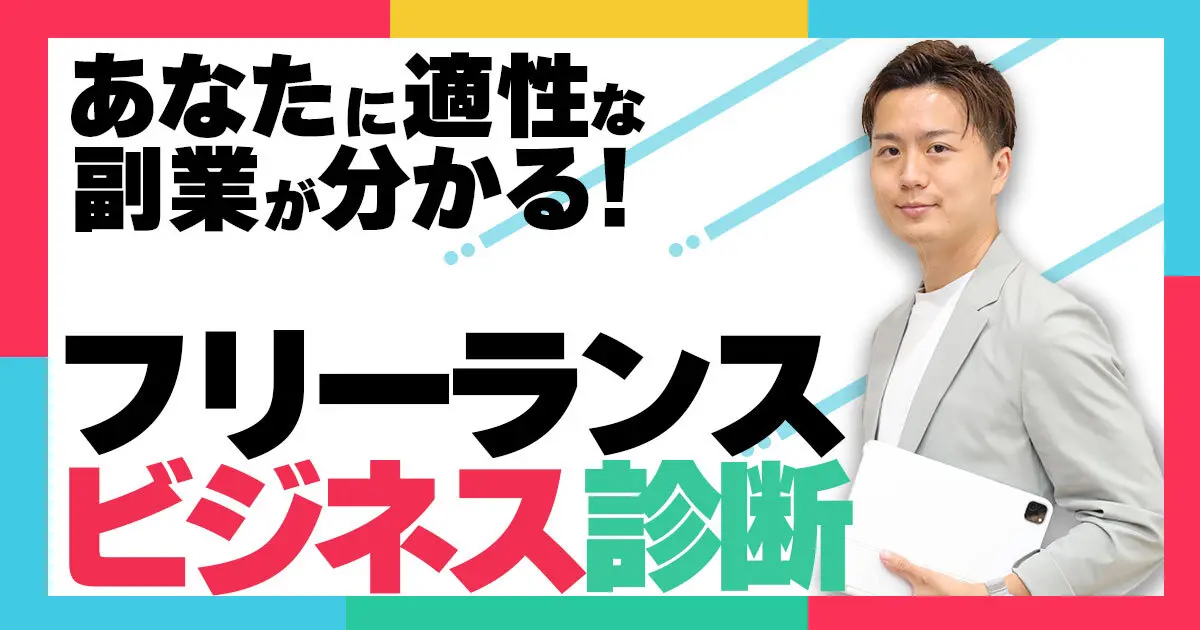どうも、フリーランスエンジニアのりゅうけんです。インフラエンジニアのみなさん、これからの将来に向けて何か対策されてますか?
インフラエンジニアという食いっぱぐれない仕事ができているものの、いつまでも需要過多の状態が続くか分からないし、スキルアップしていきたい・・そう考えている人は少なくないと思うんです。
今日はそうした人に向けて、これからの将来を不安に思うインフラエンジニアが何をしていくべきなのかについて語っていきたいと思います。その答えはズバリ「クラウド」を勉強すること。
インフラエンジニアがクラウドのスキルをつけるとマジで最強です。さっそくその理由について説明していきたいと思います。
目次
なぜインフラの将来が不安なのか

インフラエンジニアになれた時点で将来安泰じゃないの?という意見も分かります。
エンジニアという仕事は今既に圧倒的な需要過多、供給不足ですし、プログラミングが必修化されたことからもこれからさらに伸びていくことが予想されているんですよね。
そんな中、インフラエンジニアとしてなぜ将来が不安になるのか。それはインフラエンジニアの仕事が「オンプレミス」から「クラウド」へとどんどん移ってきているからです。
エンジニア業界全体に言えることなんですが、今のスキルで一生涯安泰ということはあり得ないんですよね。いつまでも「オンプレミス」専門のインフラエンジニアでいると、仕事がどんどんなくなっていくと予想されています。
オンプレミスはプログラマーでいうとcobolみたいなノリ的な話
プログラミングでcobolという言語があるのをご存知でしょうか。今の環境でも使われてはいるけれど、ちょっと時代遅れ感があるプログラミング言語です。
インフラエンジニアにおけるオンプレミスは、このプログラミング言語におけるcobolの立ち位置に似ているんですよね。まだ現役で使われているけど、次世代の性能には適うはずもなく飲み込まれていくことが目に見えている。
今までオンプレミスの技術だけに取り組んでいたインフラエンジニアは、これから先の将来で扱える仕事が少なくなって苦労するかもしれません。
AmazonやGoogleに低レイヤーはお任せできるようになっちゃう的な話
次世代のクラウドがインフラエンジニアの需要を奪う理由として、クラウドがこれまでのオンプレミスに比べてかなり構築が簡単になっているということが言えます。
Amazonが提供するAWS、Googleが提供するGoogle Cloud Platformが主なクラウドインフラを担うものなのですが、機器の設置、設定など基本的なところがネット上であっという間に出来上がってしまうんです。
つまり、インフラエンジニアのやるべき仕事を、AmazonやGoogleが仕組み化してしまったということ。今後は低レイヤーに関してはAmazonやGoogleにお任せとなる未来が見えますね。
クラウドはインフラエンジニアにとって唯一の活路

そういった将来が見えている状況で、僕たちインフラエンジニアとしてできる唯一の打開策が、クラウドインフラに関するスキルを身に着けてしまうことです。
インフラエンジニアの中でも、「クラウド化」という言葉がかなり浸透してきましたね。
ここまでクラウドが台頭したおかげでインフラエンジニアの仕事がなくなるとか、マイナスな話が続きましたが、クラウドを習得できるとインフラエンジニアにとってたくさんのメリットがあるんです。
クラウドの素晴らしさ1:物理作業(DC)から解放される
僕が初めてクラウドに触れたとき、この部分に一番衝撃を受けました。今までオフィスとデータセンター(DC)を行き来して設定作業や構築を行っていたと思うんです。
それこそ障害が起こった時には急いでDCに急行して作業するとか当たり前でしたよね。
クラウドだとスイッチやサーバを作り上げるのも、新たに台数を増やす場合も、障害対応を行う場合さえもネットを通じてオンラインで操作可能です。そもそもクラウドで動かしていると故障するということもあり得ないので安心ですね。
DCで作業するのって、実機を持ち運びしたりすることもあって割と体力勝負みたいなところもあるんですが、クラウドだとそんな苦しさもありません。移動する手間もなくなってまさに一石二鳥。
クラウドの素晴らしさ2:需要が増加傾向で高単価
エンジニアの案件単価に関しても申し分ありません。
これまでスイッチやサーバを物理的に用意して構築していたために、スペース的にも金額的にもコストがかかっていましたが、クラウドになるとこれらのコストが一気にカットできる。
そのうえクラウドを扱えるインフラエンジニアはまだまだ少ないので、需要は増えるのに供給が少ない状況なんです。なので、クラウドを知っておけば高単価な案件を手にすることができるというわけですね。
クラウドの素晴らしさ3:コードを学ぶ機会がある
インフラエンジニアは、プログラマーと違ってガンガンコードを書く機会があるわけではありません。実際にプログラミングができなくてもインフラエンジニアになる人もいるほど。
ですが、クラウドを扱うようになると必然的にコードを学ぶことができます。
Infrastructure as Codeと言われるインフラの構築を自動化するプロセスがあるんですが、このプロセスがクラウドでは普及しているんです。つまり、インフラがソフトウェア化され、ネットワークやサーバをプログラムで操作することが可能になったということ。
プログラミングを操れるインフラエンジニアは現場でも汎用性が高く評価されやすいので、自身のスキルアップにつながること間違いなしですね。
クラウドの素晴らしさ4:アプリ開発も容易になる
クラウドの素晴らしさは、インフラだけに当てはまるわけではなく、アプリ開発においてもすごくいい影響を与えます。インフラと同じく開発でも、リモートでネットさえあればOK、故障すらない環境で安心して作業を行えるのは非常に有難い。
従来は社内に保存してあったデータとかリソースをクラウド上で管理できるので、場所や時間といった制約から解放されアプリの開発に伸び伸びと専念することができるんです。
AWSでいうと、EC2とRDSで自前でサーバとDB用意して、大規模アクセスに耐えうる構造をさくっと作るだけ。めちゃ簡単に開発に専念できる環境が整います。
オンプレ偏重ではライフスタイルは変えられない

クラウドインフラにかなりの価値やメリットがあることを分かっていただけたでしょうか。これだけのプラス要素があって、クラウドに移行していかない理由がもはやないんですよ。
企業も官公庁も今後必ずクラウドに移ることは確定しています。それが早いか遅いかの違いだけ。
だったら、今まだクラウドインフラを扱えるエンジニアが少なくて、引っ張りだこの時代に身に付けておいたほうが断然お得じゃないですか。
オンプレミスだけを扱える状態だと案件数も徐々に少なくなっていくでしょうし、生活スタイルを変えていきたいならクラウドインフラを扱えるようになっておくべきですね。
クラウドを学ぶならスクールで

ということで、インフラエンジニアならクラウドを学んどくべきっていう話でした。ですが、インフラエンジニアのクラウド技術は、世に出てきてまだ月日が浅いこともあってしっかりとした勉強法が確立されていないのが現状です。
つまり独学だと結構厳しめです。そこで僕がおすすめしたいのが、クラウド技術を学ぶためにスクールに入って勉強するという方法。以前はネットワークやサーバー周りだけを扱うスクールが多かったのですが、ここ最近はクラウドも学べるスクールがどんどん増えてきています。
転職前提にはなっちゃうのですが、紹介しているスクールはどこも無料でクオリティも自信を持ってオススメできるので、ぜひ。
さいごに:新しい技術に意欲的でなくなったらエンジニアは終わり
確かに現在、エンジニアは需要も高く、高収入が狙える仕事ではあります。でも、それはエンジニアに求められている技術や知識が、常に最新鋭のものが多いことの裏返しなんですよね。
移り変わりが激しい業界なので、数十年前のスキルじゃお話にならないこともしばしば。
だからこそ、エンジニアは常に最新の動向や流れに敏感になっておかなければいけないし、スキルアップしていく必要があるんです。そうじゃないと不要なエンジニアに成り下がるので。
逃げ切りサロンではAWS勉強会とかやってるよ
ちなみに僕の主催するオンラインコミュニティの人生逃げ切りサロンでは、最近AWSの勉強会が行われています。
スクールではなくあくまで勉強会なので、出された課題を一緒にこなしていくという感じですが、内容を見るとかなり深い内容まで突っ込んで行っているので、ちゃんと完走すればそのままAWSエンジニアとしてフリーになれそうなレベルです。
興味がある人は、ぜひこちらも覗いてみてくださいね。